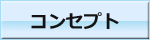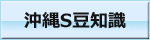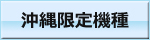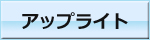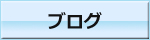沖縄で圧倒的な支持と長い歴史を誇るトリプルクラウン。
なんで沖縄だけトリプルクランが流行ったのか?という謎を本土の人はおろか沖縄の人でさえ疑問だらけ。
その理由を私が勝手に推測。
あくまでも私的観点による推測ですので、そういう線もあるかもねという楽な考えで読んでください。

時代は遡る3号機時代
まずトリプルクラウンが増殖する前の状態はどうだったのかというところからスタートします。
4号機以前の3号機時代、沖縄のほとんどの店舗において現在主流である箱型筐体のパチスロは導入されておらず、アップライト筐体がメインで設置されておりました。
当時設置されていたアップライト筐体として、APEX701Z(サミー工業)・フェニックス(高砂電器)・マリーナ(メーシー)などがあったわけですが、その全てがレバーオンで告知する先告知タイプだったのです。
4号機以前から、沖縄では先告知が根付いていたと言えます。
すでに先告知が根付いていたことから、後々4号機に入れ替える際に告知できるタイプであることが、必須条件となったのではないでしょうか。

4号機時代へ突入
さて、本土では1992年にチェリーバーが登場し、4号機時代へ本格突入します。93年にはニューパルサーも登場し、パチスロ市場も一気に人気が再燃していきます。
その頃の沖縄なんですが、何も変化がありません・・・。何事もないかのように、アップライト筐体だけの設置という状態でした。
裏モノ規制によって3号機が撤廃され、4号機への舵取りとなったのですが、4号機がスタートして2年経っても沖縄では裏モノが蔓延した状態だったわけです。
もちろん沖縄だけ例外、なんてことはなかったと思いますが、沖縄だけ遅々として入替が進まなかったのは、94年まで30φ4号機が発売されなかったから。
やはりこれに尽きるかと思います。
いくら警察から指導があったとしても、その当時の沖縄はパチンコ3:パチスロ7というシマ構成でしたから、これらを25φしか発売されていない4号機に入れ替えるとなると、
設備からなので費用が莫大なのは素人目に考えても容易です。ある程度警察も黙認していたのではないでしょうか。入れ替えを行った店舗もあったかもしれませんが、私の記憶では1店舗もありません。

ついにその時はやってくる
いよいよ1994年に4号機30φが発売となるわけですが、順次入れ替えになったかと言うとそうでもありません。それでも何事もなくアップライト筐体が鎮座しているわけです。ちなみに主役となる初代トリプルクラウンⅡ-30(マックスアライド)が発売されたのも、この94年。ですが、日の目を見るのはもう少し先。
そんな平穏な沖縄に、1994年12月とある大きな事件が起きます。(事件の内容に関しましては、現在運営している店舗の名誉もございますので、詳細控えます。)
この事件と因果関係は明確ではありませんが、この頃から急速に4号機への入れ替えがスタートしていったと記憶しております。
沖縄の店舗が早急に入れ替えへという流れの中で、選択肢は多くなかったでしょう。実際、95年初頭までに発売されている30φ4号機は10~15機種程度。
さらにその中で先告知が標準装備されている機種となると、もうこれしかないという感じだったんじゃないでしょうか。
そうここで初めて、「トリプルクラウン」に白羽の矢が立ったのでは?と思っています。

王座へ君臨する
1995年になると、沖縄の各店舗で一気に4号機への入れ替えが進みます。もちろんその中心にあったのはトリプルクラウンであるのは言うまでもありません。
当時の沖縄の設置状況として、アップライト筐体時代からそうだったのですが、1店舗1機種多くても2機種というのが主流。
さらに大型店舗が多く、前述したようにパチスロ比率が高いため、パチスロ300台総トリプルクラウンなんていうのも当たり前。
もちろん他の4号機を設置した店舗もありました。ダイバーズXX-30・クリエーター-30・アラジンマスター-30などは見たことがありますが、ここ沖縄においては全て先告知できるように改造されておりました。
告知ランプのない機種においては、配当表などのランプがレバーオンで点滅したりと。特にダイバーズはリーチ目というメインのゲーム性が封殺されているので、流行るわけもなく淘汰されていくわけです。
結局、先告知に慣れた土地柄に、先告知を標準装備していない機種はどれも太刀打ちできなかったのではないでしょうか。
強力なライバルがいない状況で、なるべくして王座へ君臨したと言えるかもしれません。
言い換えれば、その当時に他の先告知または告知機種があれば、取って代わっていた可能性もあったでしょう。

磐石の布陣へ
ここで、多くの人が思う疑問にも触れておきます。
ジャグラーは太刀打ちできなかったのか?
まず残念なことに、初代ジャグラーの発売開始は1997年まで待つことになります。さらに、初30φ仕様のゴーゴージャグラーS-30は2003年発売となり、トリプルクラウンの牙城を崩すには時すでに遅しという印象です。
本土でどんな告知機種をもってしてもジャグラーの牙城を崩せないように、先にトリプルクラウンの王国をつくってしまった沖縄ではジャグラーをもってしても崩せない。といった感じでしょうか。
4号機・AT・ST・5号機と経て、そのシマ構成比を減らしたり増やしたりしながら、変わらない定番として君臨するのはジャグラーと似たような歴史を築いていると言えるでしょう。
唯一ジャグラーと違うのは、トリプルクラウンという冠には複数メーカーが関わっている点。
こちらはまた複雑なので、別で特集できればと思います。
以上が記憶と妄想によるトリプルクラウンが沖縄で定着した理由でした。あくまで半分妄想ですので、誤認しないように。